-
-
発熱時にすぐに冷やすのはNG!?
Posted at , on 2月 25, 2016
発熱したときのメカニズム
風邪を引けば、風邪のウイルスを退治しようと体内の白血球などの活動を活発にするために、発熱して体温を上げます。
まずは体内にウイルスが入り込むと、マクロファージや白血球がウイルスを食べます。
ウイルスと体内の免疫が戦いを始めますのでその間に、サイトカイニンという物質を免疫が作り出します。
サイトカイニンが血液によって脳まで到達しますが、その先は血液脳関門があり通れないので、情報伝達物質のメディエイタを作りだし、それが視床下部に届きます。
視床下部に届くと体温調節中枢が発熱を開始し、体温が上がっていきます。
発熱と共に、血管が収縮したり発汗を抑えるなど熱が逃げるのを防ぐように体が働いて、体温が上昇していくのです。熱が出始めの頃は冷ますのではなく、体温が逃げないようにします。
厚手の服を着たり布団をかけたりして、室温も高めにしておくと良いです。
高熱で汗をかけば風邪が治りやすいという根拠はありませんが、汗をかいて湿度を高くすることは、湿度に弱い風邪ウイルスには有効です。
ただし汗をかいたままでは体を冷やして体調を悪化させることがあるので、こまめに着替えるようにしましょう。
汗をかくと体の水分が失われるので、脱水症状にならないように水分補給も行います。リンパを中心に冷やす
体を冷やす場合はリンパを中心として冷やすと良く、首の回りや脇の下などを冷やすようにします。
リンパは免疫気管の一つなので、細菌を退治する働きがあります。
リンパが活発に働き熱を発生させますので、リンパの集まる場所を冷やして正常に機能するようにします。体は末端の手足よりも内部の心臓や脳などの方が体温は高くなり、末端ほど熱は逃げやすいです。
体温が高いということは血液の温度も高くなっているということなので、血液の温度を下げる必要があります。
このために血液が皮膚近くを通っている首の回りや脇の下を冷やす方が、効率的に熱が下がります。
熱を下げるためには保冷剤を用意しておくと便利です。
おでこに保冷剤などを当てて冷やすという方もいるかもしれませんが、気持ち良くはなりますが、熱を下げる効果はほとんど無いので、脇の下などを冷やした方が良いです。鼻水や咳が出る場合は、体内のウイルスを体外に排出しようとする行為であり、無闇に咳止めなどで止めない方が良い場合もありますが、長く続くようなら風邪以外の症状も考えられますので、病院でみてもらった方が良いです。
高熱が続くようならインフルエンザになっている可能性もあります。
発熱によって脳にダメージが出るのではないかと心配する人もいるかもしれませんが、発熱だけでは滅多にダメージを与えることはありません。
-
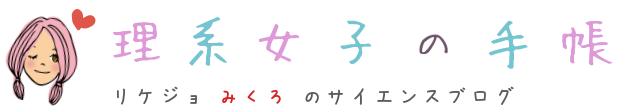

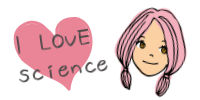 ☆名前:みくろ
☆名前:みくろ