-
-
深海魚と光の秘密について迫る!
Posted at , on 2月 15, 2016
光の届かない深海
深海にも魚は生息しており、その数は多数あります。
その魚の姿は、普段私たちが見ているような魚とは少し違うような形をしており、目のない魚や体が透明になっている魚など、およそ私たちの想像の及ばない造形を見せてくれます。深海魚が淡水魚などとはかけ離れている形をしているのは、これは深海は光が届かない場所であるというのが大きく関係しています。
そのために深海では光は生物の姿を映し出すという役割はしておらず、深海魚も他の方法で対象物を探るものも多いです。
また深海での光は貴重なので、様々な使われ方がします。深海での光の役割
深海魚たちは光を様々な使い方をしています。
そして光ではなく他の物で他の生物を探る深海魚もあり、例えば赤外線を使って探すオオクチホシエソのような魚もおり、この魚は深海で赤い光を使用してサーチライトのように対象物を探します。
暗い中では赤は見つかりにくいために、このように進化してきたのです。深海魚として有名なのはチョウチンアンコウであり、この魚は先端を光らせることで、これをルアーのようにして魚をおびき寄せて捕らえます。
このような深海魚はいくつかあり、例えば光を口の中までもっていき、そしてそのまま魚が口の中に入ると、閉じて食べてしまう魚もいます。このように光は探索やおびき寄せるのにも使われますが、防御にも使う生き物もいます。
それがプランクトンのガウシアであり、通常は深海を回遊してますが、突如魚などに襲われると激しく発光し、敵が驚いている間に逃げます。
防御のために光を使う生物もいるのです。光は求愛に使う生物もおり、それがミツマタヤリウオです。
雄は大きな発光器を備えており、成魚になるとほとんどエサは食べなくなり、その代わりにこの発光器を使って、求愛を行い、生殖のために使うのです。深海では光は届かないといっても、生物がいればその影はうっすらと出はありますが出来てしまいます。
多くの魚はそのような影を頼りにして獲物を探すような場合も多く、影が出来ると致命的な場合もあります。
しかしこの影を消すことが出来れば他の生物から見つかりにくくなるのではないでしょうか?
それを多くの深海魚は光を使って行っています。深海1,000mぐらいまでは太陽の光もうっすらとでは届き、生物がいると影を作ります。
そこで深海魚はお腹に発光器を備えており、この発光器を届いている太陽の光と同じぐらいの強さで発光させると、自分の影を消して相手から見つかりにくくなるのです。
深海1,000mぐらいまでの太陽の光が僅かに届く範囲で生息している魚の多くは、この発光器を備えていると考えられています。
このように深海魚にとっての光は、ただ照らすだけのものではないのです。
-
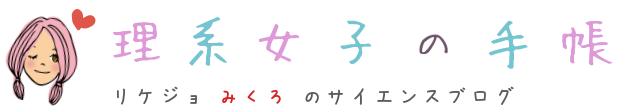

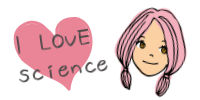 ☆名前:みくろ
☆名前:みくろ