-
-
神秘的な冥王星
Posted at , on 8月 27, 2017
・無人探査機が掴んだ冥王星の真実とは?
太陽系に存在する星のひとつである「冥王星」。
1930年に発見された冥王星は、なんと地球から数10億kmも離れたところにあるのだそうです。
そこにNASAは無人探査機を飛ばし、冥王星をキャッチすることに成功しました。
数10億kmも遠い、それも宇宙に探索機を飛ばすこと自体がすごいですが、探索機は一体冥王星のどんな真実を発見したのでしょうか。・やはり冥王星は生きていた?
冥王星が地質活動を行っている可能性については、以前から考えられていたそうですが、星自体が氷に覆われた天体であるため、そうした環境において地質活動が行われているあ可能性はほぼないと考えられていました。
しかし、今回の無人探査機の調査で、氷が移動していることが確認されました。氷が動いているということは、何らかの熱によって氷が溶けているということ。
冥王星の内部には熱があり、その熱が氷を溶かして地質活動を行っているという事実が明らかになったのです。無人探査機がとらえた氷の動きは、地球上にある氷河の動きと似ているそうです。
とはいえ、冥王星の氷は窒素が固まったものと考えられているため、地球とまったく同じ条件で地質活動が行われているというわけではないようですが、冥王星にある「ライト山」と「ピカール山」では、窒素や水など、何らかの物質によってできた氷が火山のように噴き出て見えます。・冥王星の衛生にも新たな発見
冥王星の地質活動がキャッチされたということだけでも大きな発見ですが、今回の調査では、冥王星の衛生である「カロン」にも、新しい発見がありました。
カロンは冥王星と同じくらいの大きさがある衛生で、無人探索機がキャチした映像によると、その天体は地質的にまだ新しく、これまでの「死んだ衛生」という認識を覆すものだったそうです。その後、無人探査機は冥王星とカロンの横を通過し、その2つの天体の様子を撮影する事に成功しました。
その画像を見てみると、冥王星の周りに幻想的な青い輪が広がっていたのです。地球から見える青空は、大気中のさまざまな微粒子が日光の青の波長を散らすことで青く見えるといわれています。
冥王星の青い輪とまったく同じものではないにせよ、この青い輪は今後の研究において、冥王星を覆う大気がどのようなものであるかを突き止める非常に有効な手がかりになると期待されています。これまでただの冷たい氷の星と思われていた冥王星が、新たな可能性を見せてくれたことで、宇宙の新たな一面を垣間見ることができそうです。
今までと同様、冥王星についてはいろいろな意見が飛び交うことになりそうですが、今後の研究結果に期待しましょう。
-
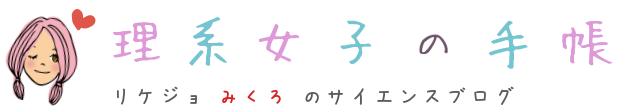
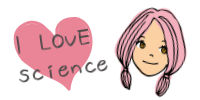 ☆名前:みくろ
☆名前:みくろ